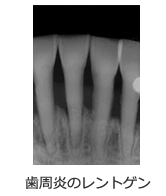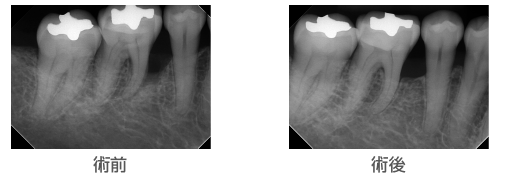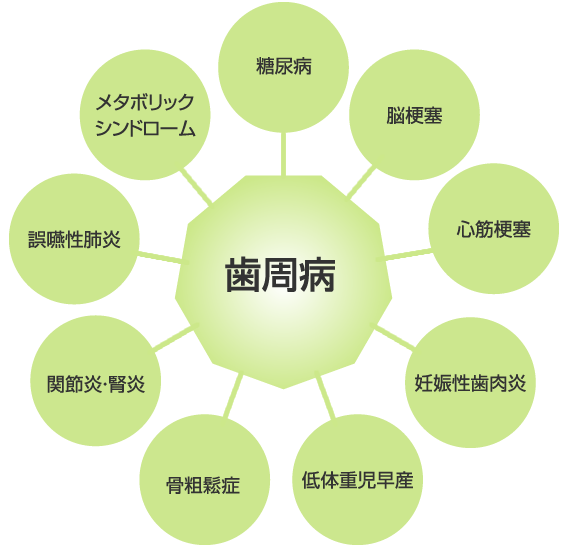2025年12月2日
年末年始診療時間のお知らせ。
年内診療は12月29日(月)20時までとなります。
年始は1月5日(月)からの診療となりますので宜しくお願い致します。
2025年10月7日
11月診療時間変更のお知らせ。
11月18日は休診日になります。
また、11月21日(金)は18時までの診療となります。
宜しくお願い致します。
2025年9月30日
10月診療時間変更のお知らせ。
10月13日(月)は休診となります。
宜しくお願い致します。
2025年9月25日
9月診療時間変更のお知らせ。
本日9月25日(木)の診療時間は、17時までとなります。
宜しくお願い致します。
2025年9月3日
10月診療時間変更のお知らせ。
10月1日は休診日になります。
宜しくお願い致します。
2025年8月26日
9月診療時間変更のお知らせ。
9月15日(月)、9月23日(火)は休診日となります。
宜しくお願い致します。
2025年7月16日
8月診療時間変更のお知らせ
8月7日(木)の午後、8月12日(火)~8月15日(金)は休診日となります。
又、8月7日(木)は13時30分までの診療となりますので宜しくお願い致します。
2025年5月10日
5月診療時間変更のお知らせ。
5月23日(金)は休診となります。
宜しくお願い致します。
2025年4月24日
5月診療時間変更のお知らせ。
5月3日(土)~5月6日(火)まで休診となります。
宜しくお願い致します。
2025年4月24日
4月診療時間変更のお知らせ。
4月29日(火)は休診となります。
尚、翌日4月30日(水)は18時までの診療となります。
宜しくお願い致します。
2025年2月28日
矯正料金変更について
4月から矯正料金変更予定になります。
よろしくお願い致します。
2024年12月14日
年末年始のお知らせ
12月29日(日)~1月3日(金)まで休診となります。
よろしくお願い致します。
2024年11月12日
11月診療時間変更のお知らせ。
11月24日(日)は13:30まで診療致します。
宜しくお願いします。
2024年9月30日
10月診療時間変更のお知らせ。
10月3日(木)は17時までの診療となります。
宜しくお願い致します。
2024年9月27日
定期検診のご連絡の仕方について。
来年1月からハガキでのお知らせを廃止させて頂きます。
その為、メールをご登録でない方はSMSでのお知らせとなりますのでご了承下さい。
2024年9月27日
10月診療時間変更のお知らせ。
10月4日(金)、10月14日(月)は休診とさせて頂きます。
尚、10月20日(日)は13:30まで診療致します。
宜しくお願いします。
2024年8月19日
9月診療時間変更のお知らせ。
9月1日(日)は13:30まで診療致します。
宜しくお願いします。
2024年8月1日
8月診療時間変更のお知らせ
8月1日(木)の診療時間は17時までとなります。
宜しくお願い致します。
2024年7月30日
8月診療時間変更のお知らせ。
8月11日(日)から8月16日(金)までお盆休みとさせて頂きます。
宜しくお願いします。
2024年7月23日
8月診療時間変更のお知らせ。
8月18日(日)は13:30までの診療になります。
宜しくお願い致します。
2024年6月28日
7月診療時間変更のお知らせ。
7月7日(日)は13:30まで診療致します。
宜しくお願いします。
2024年5月28日
6月診療時間変更のお知らせ。
6月9日(日)は13:30まで診療します。
又、6月21日(金)は臨時休診となりますので宜しくお願い致します。
2024年4月26日
5月診療時間のお知らせ。
GWは、暦通りのお休みとなります。
宜しくお願い致します。
2024年4月15日
5月診療時間変更のお知らせ。
5月26日(日)は13:30までの診療となります。
宜しくお願い致します。
2024年4月1日
4月診療時間変更のお知らせ。
4月9日(火)は臨時休診とさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
2024年3月11日
4月診療時間変更のお知らせ。
4月14日(日)は13:30まで診療します。
宜しくお願い致します。
2024年2月20日
3月診療時間変更のお知らせ。
3月6日(水)は16:30分最終受付となります。
又、3月17(日)は13:00最終受付となりますので
宜しくお願い致します。
2024年2月20日
2月診療時間変更のお知らせ。
2月24日(土)は16:30最終受付となります。
宜しくお願い致します。
2024年1月15日
2月診療時間変更のお知らせ。
2月18日(日)は13:30までの診療となります。
宜しくお願い致します。
2023年12月12日
1月診療時間変更のお知らせ。
1月14日(日)は13:30まで診療致します。
宜しくお願いします。
2023年11月21日
年末年始のお知らせ。
年末は12月29日(金)までの診療となります。
尚、年始は1月5日(金)からの診療となりますので宜しくお願い致します。
2023年11月21日
12月診療時間変更のお知らせ。
12月3日(日)は13:30までの診療になります。
2023年9月21日
10月診療時間変更のお知らせ。
10月1日(日) 10月29日(日)は13:30まで診療致します。
宜しくお願い致します。
2023年9月20日
8月診療時間変更のお知らせ。
8月22日(金)は18:30までの診療になります。
よろしくお願いします。
2023年8月25日
9月診療時間変更のお知らせ。
9月10(日)は13:30まで診療致します。
宜しくお願い致します。
2023年8月1日
8月診療時間変更のお知らせ。
8月11日(金)~8月18日(金)まで休診とさせて頂きます。
8/10(木)、午後は休診とさせて頂きます。
尚、12日(土)は矯正のみの診療となりますので宜しくお願い致します。
2023年7月7日
8月診療時間変更のお知らせ。
8月27日(日)は13:30まで診療を行います。
宜しくお願い致します。
2023年6月23日
7月診療時間変更のお知らせ。
7月18日(火)は休診とさせて頂きます。
宜しくお願いいたします。
2023年6月9日
7月診療時間変更のお知らせ。
7月2日(日)は13:30まで診療を行います。
宜しくお願いします。
2023年4月28日
6月診療時間変更のお知らせ。
6月4日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2023年4月28日
5月診療時間変更のお知らせ。
5月28日(日)の診療ですが、今月の日曜診療は無しとさせて頂きます。
申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
2023年4月18日
5月診療時間変更のお知らせ。
5月28日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2023年4月14日
5月診療時間変更のお知らせ
5月17日(水)は18:00までの診療になります。
よろしくお願いいたします。
2023年3月24日
4月診療時間変更のお知らせ。
4月16日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2023年3月11日
4月診療時間変更のお知らせ
4月10日(月)は18:00までの診療になります。
よろしくお願いいたします。
2023年2月3日
3月診療時間変更のお知らせ。
3月20日(月)は休診とさせて頂きます。
よろしくお願いします。
2023年1月27日
2月診療時間変更のお知らせ。
2月10日(金)は11日(土)矯正診療の振替休日になります。
よろしくお願いします。
2023年1月13日
2月診療時間変更のお知らせ。
2月19日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願い致します。
2022年12月26日
12月診療時間変更のお知らせ
12月27日(火)は13:30までの診療になります。
よろしくお願いします。
2022年12月9日
1月診療時間変更のお知らせ。
1月22日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年12月9日
年末年始のお知らせ。
12月30日(金)~1月4日(水)まで休診となります。
よろしくお願い致します。
2022年11月11日
12月診療時間変更のお知らせ。
12月14日(水)は18:00までの診療になります。
よろしくお願いいたします。
2022年11月4日
12月診療時間変更のお知らせ
12月11日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年10月28日
11月診療時間変更のお知らせ
11月20日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年9月13日
10月診療時間変更のお知らせ
10月30日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年8月13日
9月の診療時間変更のお知らせ
9月25日(日)13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年8月13日
9月の診療時間変更のお知らせ
9月12日(月)、9月14日(水)は18時までの診療になります。
よろしくお願いします。
2022年7月9日
8月の診療時間変更のお知らせ
8月21日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年7月9日
8月の診療時間変更のお知らせ
8月12日(金)は18時までの診療になります。
よろしくお願いします。
2022年7月9日
7月の診療時間変更のお知らせ
7月24日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年7月9日
7月の診療時間変更のお知らせ
7月11日(月)は18:00までの診療になります。
よろしくお願いします。
2022年5月21日
6月の診療時間変更のお知らせ
6月29日(水)は18:00までの診療になります。
よろしくお願いします。
2022年5月21日
6月の診療時間変更のお知らせ
6月12日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年5月2日
5月の診療時間変更のお知らせ
5月15日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年4月2日
4月の診療時間変更のお知らせ
4月17日(日)は13:30まで診療を行います。
よろしくお願いします。
2022年4月2日
4月の診療時間変更のお知らせ
4月6日(水)は18:30までの診療になります。
よろしくお願いします。
2022年3月31日
2022年4月より、診療時間が変わります。
月水金;20時まで、火木土;18時までとなります。
2022年3月29日
2022年4月より、日曜・祝日が定休日となります。
営業時間についても変更がございます。ご確認のほど、よろしくお願い致します。